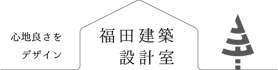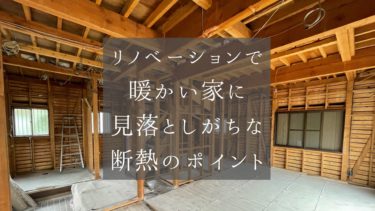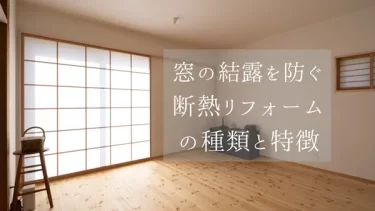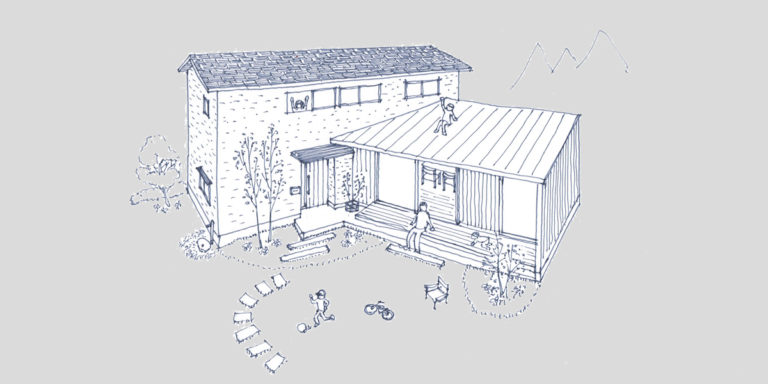現在の住宅現場で一般的な断熱材であるグラスウール。価格が安価であるため多く採用されていますが、種類や施工方法を間違うとかえってリスクが伴います。今回は断熱材の説明やグラスウールの施工のポイントなどを事例を交えて紹介します。

そもそもグラスウールとは
グラスウール(ガラス繊維)はガラスを高温で熱し、綿状にしたもので、原料はリサイクルガラスが使われているエコな材料です。ガラス繊維により空気が閉じ込められた非常に細かい部屋を無数につくることで温度が伝わりにくくなり断熱効果が得られます。
なぜ断熱材が必要なのか
昔の家は木製窓で隙間風が多く、こたつや囲炉裏で暖を取っていました。その後、窓がアルミサッシに変わり、気密性が高くなりました。ここで問題になったのが結露です。暖かい空気が室内に密閉されることで窓だけでなく、壁や天井にも水滴が付くように・・・。こうして断熱材というものが必要になったわけです。断熱材は冬の寒さや夏の暑さから守る保温材としての役割だけではなく、温度差から生じる結露を防ぐためのものでもあるのです。結露はカビの発生による室内環境の悪化や壁の中だと構造体の耐久性にも影響するため、軽視できません。
なぜ袋入りグラスウールを使用するのか
断熱材には様々な種類がありますが、最も一般的なのがグラスウールやロックウールなどの無機繊維系のものです。理由は価格の安さと施工の速さです。中でも袋入りのタイプは壁の中に湿気が入るのを防ぐ防湿フィルムがセットになっているため、特に施工スピードが速くなります。断熱材の種類によっては専門業者による工事が必要な場合があることに比べ、袋入りのタイプは大工さんで工事が可能なことが、多く使われている理由の一つです。
施工のポイント(リノベーションの事例)
安くて速いグラスウールですが、いくつか注意するポイントがあります。実際リノベーションで採用した際の事例をもとに紹介します。
現在の新築住宅において、尺寸法による単位から91㎝という基準が多く採用されています。つまり1坪=畳2枚分が182㎝×182㎝となります。それに合わせて建築材料のメーカーも商品を作っています。しかし、少し前の家では95.5㎝や97㎝など広めになっていることがあり、同じ6畳の部屋でも広さが違います。
今回のリノベーションの現場では97㎝という単位でつくられていました。そこで問題なのがグラスウールのサイズです。多くの家の標準が91㎝なので、断熱材メーカーもそのサイズに合わせて作られています。そのまま使うとスキマができた状態になるわけです。
ではどうするかというと、各メーカーには袋入りのグラスウールと裸のグラスウールの2種類があります。袋には防湿機能があり、その袋を膜のように施工することで、室内の水蒸気が壁の中に入らないようになり、壁内の結露を防ぎます。ただ今回はその袋入りのサイズが合わないため、裸のグラスウールを採用し、後から防湿のフィルムを貼るという2段階の施工にしました。これにより壁には隙間なく断熱材が入り、湿気も防ぎます。
2種類の施工スピードを考えると袋入りが圧倒的に早いです。しかし、現場に即したものを使わないとせっかくの断熱材が100%機能しません。今回壁には裸のものを採用しましたが、天井はサイズの制約がなかったため、袋入りを使っています。
リフォームに限らず、新築住宅においても、グラスウールの断熱材の施工方法が間違っていることがよくあります。隙間なく入れることと、室内側で防湿層をしっかりと形成することがとても重要です。

ピンク色のものが袋入りグラスウール。その右の白い束が裸のグラスウール。

柱の間のサイズに合わせて断熱材を切って入れます。その後防湿フィルムで全体を覆います。

出窓の壁は盲点かも。こちらも断熱材をしっかり入れてもらいます。
家で過ごす時間が増え、暮らしの質や快適性が注目されています。昨年末、熊本でのリノベーション工事が終わり、無事引渡しができました。今回の工事のポイントは「使い勝手の良い間取り」「断熱性の強化」「自然素材による安心な空間」築3[…]
戸建てリノベーションの現場です。内部の解体工事がほぼ終わり、すっからかんになりました。家の中を見通せるとかなり広く感じます。壁に隠れていた筋交い(斜めの材)をチェック。すべて図面通り入ってました。そして梁の位置と大きさを確[…]
暖房が必要な季節になってきました。部屋を暖めて、外との気温差が大きくなるほど、窓には結露が・・・。窓は熱が逃げやすいため、対策が必要です。窓の断熱性能を高めるためには室内と外との間に空気の層をつくることが肝[…]